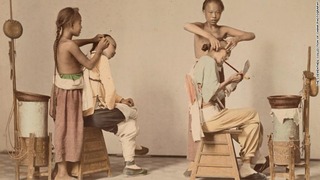もう1つの地球を探せ 「プラネットハンター」という仕事
米航空宇宙局(NASA)は2014年、生命が存在する可能性がある「ハビタブルゾーン」内に地球大の惑星を発見。ケプラー宇宙望遠鏡を使って発見されたことから「ケプラー186f」と名付けた。
地球から約500光年と比較的近い距離に位置し、地球より10%大きい。NASAはケプラー186fの発見について、「地球に似た惑星を見つけるうえで重要な一歩」としている。ケプラー186fは太陽の半分ほどの大きさの赤色矮星の周りを回っている。
15年には、太陽によく似た恒星を周回する「ケプラー452b」も発見された。地球の「いとこ」とされ、地球より60%大きく、公転周期は385日と地球に非常に近い。
現在の技術では太陽系外惑星の大きさや恒星からの距離くらいしか知ることができないのが現状だ。しかし今、それが変わりつつある。
空に新しい目が登場
NASAは17年、これまで系外惑星の大半を見つけてきたケプラー宇宙望遠鏡に代わる新しい目として、「トランジット系外惑星探索衛星(TESS)」を打ち上げる見通しだ。