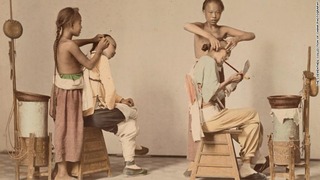インドの謎の鉄柱、1600年経った今もさびない理由とは?
芸術の世界で言及されているものもある。プリトビーラージャ3世統治下のチャーハマーナ朝に仕えた詩人チャンド・バルダーイーが書いた叙事詩「プリトビーラージ・ラーソー」では、この鉄柱が重要な意味を持つ。
「バルダーイーは、ラーソーの鉄柱はヒンドゥー教神話に登場するヘビの王シェシュナグの蹄(ひづめ)で、地球を支える釘(くぎ)だと表現している」とビクラムジット氏は説明した。
「ラーソーでは、悲惨な結果になるというバラモンたちの警告にもかかわらず、ラジャ・アナンパルがこの釘を引き抜こうとしたことが語られている。釘が引き抜かれると、シェシュナグの血と思われる赤い基部が現れ、地球の破壊を恐れてパニック状態になった。アナンパルはすぐに釘を再設置するよう命じたが、きちんと固定されていなかったため、緩んでしまった。バルダーイーは、この出来事がデリー(Delhi)の俗称『ディリ(Dilli)』に影響を与えたと示唆している。これはヒンディー語で『緩い』を意味する『ディリ(dhilli)』をもじったものである」
文化的意義と保存への取り組み
ある言い伝えによれば、この柱に背を向けて立ち、両腕を後ろに回し、両手をつなぐことができたら願いがかなうとされ、柱には歴史的な価値を超えた精神的な意味も込められている。
だがインド考古調査局(ASI)は、人為的な影響を最小限に抑えるため、柱の周りにフェンスを設置した。
修復建築家で文化遺産の専門家であるプラヤ・ナガル氏は、鉄柱周辺の建物が長年にわたり取り壊され、再建されてきたにもかかわらず、この柱が保存されていることに注目している。
同氏は、柱の建造に使われた技術を、単に古代の起源を認めるだけでなく、新たな視点から見れば、金属抽出といった工程に伴う環境への悪影響を考慮して、持続可能な代替材料の開発に同様の技法を活用する道が見つかるかもしれないとCNNに語っている。
「単に保存され、驚嘆される遺物や記念碑を超えて、伝統的な知識や先住民の慣習の宝庫として歴史を見ることが不可欠だ。この包括的なアプローチは、より持続可能な未来への道を切り開く可能性を秘めている」