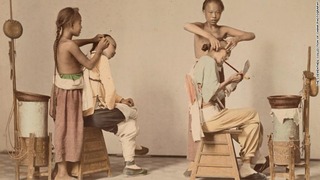カメのおしゃべりやイモリのげっぷ、鳴かないと思われていた50種以上の鳴き声確認
ムカシトカゲを加えたのは、フィールドワークで鳴き声を聴いたというニュージーランドの爬虫類専門家に出会ったことがきっかけだった。今回の調査ではムカシトカゲの特徴的な鳴き声も収録した。
一方、アシナシイモリの声は特に予想外だったと研究者は言い、「アシナシイモリが頻繁に音を立てることを発見して本当に驚いた。しかもとても面白かった」と振り返る。収録されたアシナシイモリの鳴き声は、猫がゴロゴロいうような音に聞こえる時もあれば、大きなげっぷの音のように聞こえる時もあった。
カメの場合、さまざまな種類の鳴き声を出す種もあれば、種類は限られるものの、同じ音を頻繁に繰り返して「おしゃべりをやめない」種もあったという。
今回の研究は、カメなどが音を出していることを示しただけで、その音を使って互いにコミュニケーションしていることを示したわけではないと研究者は解説する。ただ、論文では、複雑なレパートリーの存在は「コミュニケーション手段」であることを示唆しているとした。
こうした鳴き声がコミュニケーションの手段として使われていることを裏付けるためには、さらなる研究が必要だと専門家は話す。
鳴き声がカメの生態に果たす役割について理解が深まれば、種の保存の取り組みにも役立つ可能性があると研究者は指摘する。「カメは脊椎(せきつい)動物の中で霊長類に次いで2番目に大きな絶滅の危機に瀕している。その保全について考えるとき、人間の騒音を問題の原因として考えたことはこれまでなかった。しかし今、そのことを考え始めるべき時なのかもしれない」