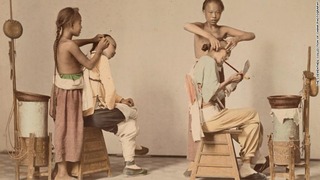犬には物とその名前を一致させる「能力あり」 研究者が主張
(CNN) 犬は特定の言葉が特定の物を指すことを理解できるとの研究結果が発表された。そうだとすると、犬は人間と同じように言葉を理解している可能性がある。
この研究を行った研究者らは、研究結果について、人間以外の動物の中で言葉を理解するための脳活動が行われていることを示す初の証拠を提示するものだと主張するが、この分野の他の専門家からは、そう結論付けるにはさらなる検討が必要との指摘を受けている。
犬が「座れ」「待て」「取ってきて」といった指示を覚え、それらの言葉に教えられた行動で反応できることは以前から知られているが、犬が名詞をどの程度理解しているのかを解明するのは容易ではない。
そこで、同研究論文の主執筆者であるノルウェーのスタバンゲル大学の准教授で、ハンガリーのエトベシュ・ロラーンド大学の研究者でもあるリラ・マジャリ氏と、同じくエトベシュ・ロラーンド大学の研究者のマリアンナ・ボロシュ氏は、犬の言語能力を把握するため、話し始める前の幼児の理解力を調査する研究で行われた実験を犬に応用することに決めた。
マジャリ氏らは、次のような実験を考案した。まず18人の犬の飼い主が、自分たちの飼い犬がすでに知っている物の名前を言う。そして、その名前に合致する物か、全く別の物のどちらかを手に取る。その間、犬の頭部に取り付けられた小さな金属ディスクが犬の脳活動を測定する。この手法は脳波記録(EEG)と呼ばれる。
この実験で、科学者らは、18匹の犬のうち14匹は、飼い主が言った名前と同じ物を見せられた時と、それ以外の物を見せられた時とで脳活動が異なることに気付いた。科学者らによると、この時の犬の脳活動は、同様の実験で人間が見せた脳活動と同じだったという。
「犬は言葉を理解するというのが我々の主張だ。つまり、犬は目の前にその物がなくても、いわゆる心的表象を作り出す」とボロシュ氏は言う。心的表象とは、その物の記憶を基に想像するイメージだという。
「飼い主が犬の心的表象と合致しない物を見せると、犬の脳の中で、ある極めて典型的な脳反応が見られた。この脳反応は、人間において、言葉の意味を理解しているか否かを示す指標として広く受け入れられている」(ボロシュ氏)
この実験では、飼い主がある物の名前を言ってから、その物を犬に見せるまで2秒間空けた。その方が、犬は飼い主の言葉を理解したのであり、単に言葉からその物を連想したわけではないと解釈しやすいためだと研究者らは論文の中で述べている。
また犬がよく知っている(と飼い主が判断した)物の名前の方が、犬に別の物を見せた時、より大きな不一致効果を生み出した。研究者らは、この事実は彼らの仮説を裏付けるものだと主張する。
エトベシュ・ロラーンド大学の声明によると、かつて行われた犬の名詞の理解を試す実験には、犬が指示された物を取って来るテストが含まれていたという。

今回の研究では、犬の脳の活動を測定した/Grzegorz Eliasiewicz
しかし、この方法で示されたのは、犬が指示通りの物を取ってくる確率は、犬が偶然それを選ぶ確率と同じということだった。もっとも、マジャリ氏も指摘するように、犬は実験中にやる気にならなかったり、他のことに気を取られたりすることもある。
これに対しEEGの場合は、このような行動による反応は不要で、研究者らは犬の「受動的理解」を試すことができたとマジャリ氏は主張する。マジャリ氏は、この方法の方が、犬が(行動などで)示せる以上のことが分かる可能性があると指摘する。
しかし、実験に参加した犬たちは、飼い主が研究室に持ち込んだ犬たち自身のおもちゃや物に反応していたにすぎず、犬たちがどれだけ飼い主の言葉を理解していたかは、研究論文の執筆者たちでさえも分かっていない。
マジャリ氏は「この研究では、犬たちが飼い主の言葉を聞いた時、彼らは自分の物(の名前を言われること)を期待していたということしか分からない」と述べ、さらに次のように続けた。
「よって犬たちが飼い主の言葉とその対象物との関係をどれだけ理解しているかは定かではない。また、カテゴリー知識も反映しているか、つまり、犬たちがボールという言葉が自分たちのボールだけでなく、多くのボール状の物を指していると考えているかも分かっていない。これは今後の研究でさらに詳しく調べる必要がある」(マジャリ氏)
アリゾナ州立大学の教授で、同大学のケイナイン・サイエンス・コラボレイトリー研究所の所長も務めるクライブ・ウィン氏は、マジャリ氏らの実験は「賢明な」コンセプトだとしながらも、この実験で明らかになったのは、犬たちが理解したのは、言葉の本質的な意味ではなく、「刺激」の後に「重要な結果」が生じるということだ、と指摘した。
ウィン氏は、この実験で飼い主が物の名前を言ってから、その物を手に取るまで間を空けるにしても、それがほんの数秒であればほとんど意味はないとし、さらに犬が、より大きな不一致効果を説明する反応を示すのは、なじみのある言葉を聞いた時に限られると指摘した。
ウィン氏によると、犬には人間が言葉を理解する上で不可欠な脳の二つの領域が存在しないため、実験を行った研究者らが強調した犬のEEGパターンは人間のそれとは異なるという。
「犬の脳波のパターンで犬が言葉を理解しているかどうかが分かると主張するのであれば、人間の脳波パターンと同じである必要がある」とウィン氏は言う。