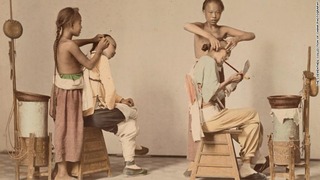腸内アルコール発酵で飲酒状態、医師にも信じてもらえない「自動醸造症候群」とは
(CNN) 呼吸からアルコール臭がする。めまいを感じてもうろうとし、力が入らない。あまりのひどさにある日、学校に通う子どもたちの昼食を作りながら意識が遠のき、キッチンカウンターで頭を打った。
アルコールは一滴も飲んでいなかった。カナダのトロントに住むこの女性(50)と夫は2年もの間、医師にその事実を訴え続けたが、なかなか信じてもらえなかった。
「女性はかかりつけ医に何度も何度も通い、2年間で7回も救急外来を受診した」。トロント大学の感染症専門医、ラヘル・ザウデ氏はそう語る。
ザウデ氏によると、医師が調べた結果、女性はアルコール濃度がリットルあたり30ミリモルから62ミリモルになることもあった。正常値はリットルあたり2ミリモル未満とされる。
この女性のような「自動醸造症候群」の患者の啓発や異常な症状に関する研究を行っている支援団体のバーバラ・コーデル代表によると、リットル当たり62ミリモルというアルコール濃度は異常に高く、命の危険さえあるとみなされる。
同氏の知人の中にそれほどの濃度に達した人はいないものの、血中アルコール濃度がリットル当たり30ミリモルや40ミリモルに達しても機能できる人は多いという。
「私は自動醸造症候群と診断された人を300人以上知っている。フェイスブックの非公開支援グループには800人を超す患者と介護者がいる」とコーデル氏。「同症候群に関して、異常に濃度が高いのに、それでも歩き回ったり話したりできる理由は分かっていない」
トロントの女性の場合、救急外来のどの医師からも飲酒の習慣について質問され、三つの違う病院で精神科医の診察を受けたが、アルコール使用障害の診断基準は満たしていないという結論だった。
「女性は自分の宗教では飲酒が認められていないと医師に説明し、夫も女性が飲酒していないことを確認した」。女性の治療を担当したザウデ医師は3日、この匿名の症例について共同執筆した論文をカナダの医学誌に発表した。
女性は7回目に駆け込んだ救急外来で、ようやく医師から「自動醸造症候群のようだ」と告げられ、専門医を紹介されたという。
ニューヨーク州の病院の消化器専門医、ファハド・マリク氏によると、自動醸造症候群の患者は信じてもらえなかったり馬鹿にされたりすることが多く、隠れ飲酒とみなされて相手にされないことがほとんどだという。
極めてまれな症例
自動醸造症候群(別名「腸発酵症候群」)は極めてまれな症例で、消化管内の細菌や真菌が、ふだんの食事に含まれる糖質や炭水化物をエタノールに変えてしまう。最初に確認されたのは1946年のアフリカの症例で、5歳の男の子が原因不明の胃の破裂を起こした。検視の結果、男の子の腹部はアルコール臭がする「泡状の」液体でいっぱいになっていた。
2021年4月のまとめによると、1974年以来、英語の医学文献には自動醸造症候群と診断された症例が20例報告されている。日本でも「酩酊症」などの症状名で報告がある。
自動醸造症候群は、人の腸内細菌の中で特定種の細菌や真菌が過剰繁殖して、消化管が蒸留タンク状態になることで起きる。
このプロセスは小腸で起きていると思われ、体にエネルギーを供給する通常の腸内発酵とは大きく異なる。
原因となる病原体は多数あるものの、ほとんどの場合、サッカロマイセスとカンジダという2種類の真菌の過剰増殖に起因する。カンジダは口内、消化管、膣(ちつ)に存在していて、善玉菌が抗生剤の投与で死滅した場合に支配的になることがある。
2013年に報告された61歳の男性の症例では、説明のつかない酔いに何度も見舞われた末に、ビールの醸造に使うサッカロマイセス・セレビシエ(ビール酵母)の腸内過多と診断された。
自動醸造症候群の患者は、代謝によって体内で大量のアルコールが生成された状態で日常生活ができることが多く、法に触れるトラブルに巻き込まれて初めて気づくこともある。
米ノースカロライナ州の40代後半の男性は、飲酒運転を確信した警官に車を止められた。男性は飲酒を否定したが、血中アルコール濃度は0.2%と、1時間で10杯飲んだ量に相当し、法律の上限の約2.5倍に達していた。
「これは私たちが思っているほどまれではない。ただめったに診断されないだけだ」とコーデル氏は言う。「歩きながらもうろう感を感じていても、ただ疲れているだけだと考える人は多いと思う。そうした人たちはアルコール発酵しているのかもしれない」
「代謝の嵐」
ザウデ氏によると、自動醸造症候群には危険要因がある。糖尿病や肝臓病、さらには炎症性腸疾患や、小腸が傷ついたり短くなったりする短腸症候群のような胃腸疾患も関係することがある。
「そうした要因が完璧なタイミングで衝突すると、リスク要因が相互に作用して代謝の嵐を引き起こし、この症候群が現れる」
ザウデ氏のトロントの患者の場合、40代半ばで尿路感染症を繰り返すようになり、そのたびに抗生剤の治療を受けたことで、代謝の嵐が起きた。腸管内の善玉菌が死滅し始め、それまでじっとしていた真菌が支配的になった。
大量の酵母は、必要とする燃料を女性の食事の糖類や炭水化物から得ていた。女性が48歳になるまでには、摂取した糖質や炭水化物はほぼ全て、体内でアルコールになっていた。
「炭水化物をあまり食べなければ症状はそれほどひどくない」「しかしケーキ1切れなど糖質の多いものを食べるとアルコール濃度が急激に上昇した。子どもたちの昼食を作っていて眠気に襲われたのもそんな時だった」(ザウデ氏)
同氏によると、自己醸造症候群の治療は、生検や大腸内視鏡検査で腸内を支配する病原菌を特定した後、殺菌剤を投与することから始まる。ただし幅広く効く殺菌剤から始めると、逆効果になることもある。
酵母の殺菌に加えて、患者は糖質を極端に制限した食生活を求められる。「糖質ゼロがベストだが、それはほとんど不可能」とザウデ氏。善玉菌を取り戻すためのプロバイオティクスも助けになることがあるという。
女性は今、抗真菌剤の服用は中止したが、再発したことを受けて低糖質の食事は続けている。症状はそれぞれの患者で異なることから、医師に相談しながら症状を管理していくことが大切だという。
「この女性の場合、夫が大きな支えになってくれ、妻の呼吸にアルコール臭がし始めるとすぐ私に電話をくれた」「この症候群の患者にとって、配偶者、友人、ルームメートなど、周りの人に兆候や症状を知ってもらい、それが起きた時は医師に連絡するか救急外来に連れて行ってもらうことが大切だ」とザウデ氏は話している。