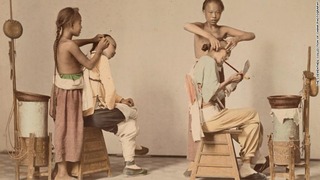世界を救う「原子力メガヨット」の構想とは
初期段階のデザインは洗練された大胆なもので、ユニークな13階建ての球体に二十数個の実験室を収容できる。航海中にデータを収集し、気候危機の緩和に役立つ解決策を導き出したい考えだ。
世界中の人が参加できるようにオープンソースのプラットフォームを活用し、量子コンピュータ-の助けも借りたい考え。量子コンピューターは量子力学の特性を活用して驚異のスピードとパワーを達成する新型コンピューターだ。
オリベラ氏がアース300に組み込みたいと考えている多くのテクノロジーと同様、量子コンピューターはまだ実用化されていないものの、グーグルやIBMなどによる実験的な研究の対象になっている。
船の定員425人のうち大半は、乗組員165人と科学者160人という二つの主要グループで構成される。
このほか学生20人や、経済学者、エンジニア、芸術家、活動家、政治家からなる専門家集団20人も乗船し、「学際的なるつぼ」(オリベラ氏)を構成するという。
この船で唯一支払いをするのは、20室のVIPスイートに滞在する富裕層の旅行者だ。一人当たり100万ドル(約1億1000万円)あまりの費用を想定し、科学関係費に充てていく。
ただ、船の排他性については忘れる必要がある。
「この船は世界中の人々が旅に参加する浮かぶコンピューターだ。つまり、乗船する富裕層はこの経験を自分たちのものだけにせず、世界と共有する必要がある」とオリベラ氏は語る。
世界を回る船
オリベラ氏はアース300を五輪のトーチやエッフェル塔のような世代を象徴する存在にしたいと思い描いている。
「この船を作ろうとしているのは、気候変動が世界的な問題であり、世界を移動できる乗り物を必要としているためだ」とオリベラ氏。さらに、海は二酸化炭素の大部分を吸収するため、地球の鼓動する心臓だとの見方も示す。
オリベラ氏はまた、乗船者にはある種の冒険や危険を体感して、閉じこもった環境で団結してほしいとも話す。「船上で築くきずなは動かないビルで育まれるものとは全く違う」という。