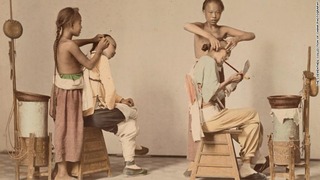超加工食品の添加物、まとめて摂取で2型糖尿病リスク増大の可能性
(CNN) 米国のスーパーなどで販売されている食品のほぼ70%を占める超加工食品。風味や色、食感を添えたり賞味期限を延ばしたり、成分の分離を防いだりする添加物が含まれている。
そうした着色料や臭素化植物油といった添加物については、これまで個々の有害性や、包装から食品に溶け出す有害物質について調べたデータはあっても、併せて摂取した場合に健康に与える影響についてはほとんど研究されていなかった。
今回、新たな研究で、そうした添加物をまとめて摂取すると、単体で摂取した場合よりも有害性が増大する可能性があることが分かった。
「特定の添加物群を摂取すると、個々の添加物による影響を超えて糖尿病のリスクが増大することが示された」。ブラジル・サンパウロ大学公衆衛生校のカルロス・アウグスト・モンテイロ名誉教授(今回の研究には参加していない)はそう解説する。
同氏によると、添加物の規制は、組み合わせではなく個々の健康に対する影響評価に基づいている。しかし添加物は単体ではなくまとまって消費されることから、そうした規制の在り方は批判の的になっていた。
食塩、油、香辛料などは調理用加工食品で、野菜や果物の缶詰、パン、チーズなどは加工食品とみなされる。一方、すぐに食べられる調理済み食品や加工肉、砂糖入り飲料やダイエット飲料などは、大規模な工業加工処理を施した超加工食品に分類される。
業界団体の国際清涼飲料協議会(ICBA)は今回の研究について「ばかげている」と反論。「この研究の主張は大きな誤解を招くもので、消費者に恐怖と混乱を植え付ける。こうした成分の安全性は、何十年にもわたる科学的証拠で裏付けられている」と強調した。
今回の研究を発表したフランス国立保健医療研究所のマチルド・トゥビィエ氏によると、食品業界は特定の種類の食品に同じ添加物を何度も組み合わせることが多い。
例えばダイエット飲料ではアスパルテーム、アセスルファムカリウム(Ace―K)、亜硫酸アンモニアカラメル、クエン酸などの人工甘味料や着色料、酸味料を組み合わせて使用する。乳化剤や人工甘味料入りのダイエットヨーグルトや、乳化剤や保存料などが入った加工パンも同じだという。
さらに、複数の食品を一緒に食べることで独自の添加物群が形成される。例えばファストフードでは工業加工されたパンを使ったハンバーガー、フライドポテト、ソーダの組み合わせが一般的。ホットドッグとポテトチップ、ソーダの組み合わせもある。そうした超加工食品をまとめて頻繁に摂取すると、化学物質群が形成され得るとトゥビィエ氏は指摘する。
8日の科学誌PLOSメディシンに発表された研究では、フランスで調査に協力した成人10万8000人の栄養状態や健康状態を分析した。この集団に対する過去の調査では、人工甘味料、キサンタンやグアーガムなどの乳化剤、加工肉に含まれる硝酸塩と、2型糖尿病のリスク増大との関係が指摘されていた。
参加者には普段食べている食品のブランドを報告してもらい、150カ国で300万を超す食品の成分などについてブランド別に分類したデータベースを使って、個々の参加者が摂取した添加物を特定。その結果を2023年12月までの医療記録と照合して、2型糖尿病の発症との関係を調べた。
その結果、添加物の組み合わせ5群のうち2群について、食事から摂取した栄養や社会人口統計学、生活スタイルとは関係なく、若干の糖尿病リスク増大と関係していることが分かった。
最初の1群は変性デンプン、ペクチン、グアーガム、カラギーナン、ポリリン酸塩、ソルビン酸カリウム、クルクミン、キサンタンガムの組み合わせだった。キサンタンとグアーガムは植物由来で、一般的に安全だとする研究もある一方で、腸内細菌の乱れや炎症との関係を指摘する研究もある。
こうした添加物はプリンなどのデザート乳製品や、チーズディップ、スープなどに含まれる。
次の2群にはクエン酸、クエン酸ナトリウム、リン酸、亜硫酸アンモニアカラメル、アセスルファムカリウム(Ace―K)、アスパルテーム、スクラロース、アラビアガム、リンゴ酸、カルナウバロウ、パプリカエキス、アントシアニン、グアーガム、ペクチンが含まれる。こちらの添加物は一般的に、甘い飲料や人工甘味料入りの飲料に使われる。
今回の研究について、栄養学に詳しい米ノースカロライナ大学のエリザベス・ダンフォード助教は「特定の添加物の組み合わせが健康に及ぼす潜在的な悪影響にスポットを浴びせる第一歩」と評価している。