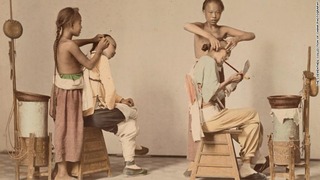抗不安薬による水質汚染、サケの回遊に変化 「恐怖感」薄れ外洋に早く到達
(CNN) 静かな小川や河川でふ化したサケは、外洋で成長するために危険な旅に出る。何百万年にもわたり、若いサケは淡水系から海へと、時に何百キロもの距離を移動してきた。しかし、現代のサケは太古の祖先が知らなかった新たな障害、回遊行動の変化を迫る薬物汚染に直面している。
研究者は最近、「クロバザム」と呼ばれる薬がサケの脳に蓄積すると、回遊する個体がより早く海に到達し、ダムも素早く突破できることを突き止めた。
一見、サケにとってありがたい変化のように思えるかもしれない。だが、科学者のグループが学術誌サイエンスに10日付で報告したところによると、人間の活動、特に向精神物質の関与で生き物の通常の行動が変わるのは危険信号であり、薬剤汚染がサケの健康や行動、繁殖をどう変化させるか全容は未知数だという。
クロバザムは下水でよく検出される薬で、中枢神経を抑制する「ベンゾジアゼピン系」の薬のグループに属する。薬の用途はてんかん発作の予防や短期的な不安治療、不安に関係する睡眠障害の治療など。ただ、アイダホ大学魚類野生生物学部のクリストファー・コーディル教授は、魚類は哺乳類と神経回路が似ているため、人間の神経化学に作用する薬の影響を受けやすいと説明する。
コーディル氏はCNNに寄せたメールで、「人間は魚類と多くの生物学的構造が共通しており、生理学的にも解剖学的にも驚くほど似ている。従って、向精神薬が魚と人間の両方の行動を変化させるのは直感的に理解できる」と指摘した。コーディル氏は今回の研究に関わっていない。
以前の研究でも、ベンゾジアゼピン系薬がタイセイヨウサケの行動を変える可能性が示されていたが、論文の共著者を務めた豪グリフィス大学環境科学部のマーカス・ミケランジェリ講師によると、これは野生のサケとは異なる条件下だったという。
ミケランジェリ氏はメールで「こうした研究は主に実験室環境で行われ、100メートル未満の短距離の移動のみを追跡するか、あるいは野生のサケが通常遭遇する水準を大きく上回る薬物濃度を用いていた」と指摘。「われわれの研究では異なるアプローチを採用している。サケの稚魚が自然河川で川から海へ回遊する全行程を追跡し、魚が環境内で実際に曝露(ばくろ)されているのと同水準の薬物濃度を用いた」と説明した。
ミケランジェリ氏によると、現地調査の結果は、医薬品汚染が世界の野生生物に突きつけるリスクの高まりを浮き彫りにするものだった。
泳ぎ続ける
新たな研究のため、研究者は700匹を超える若いサケ「スモルト」を用いた試験を実験室と現地環境で行った。2020年と21年には音波発信タグを利用し、スウェーデン中部のダール川を泳ぐ数百匹のスモルトを遠隔追跡した。
回遊するスモルトは川を下って貯水池へ入り、急流を抜け、二つのダムを越えてようやくバルト海に達する。所要日数は10~13日だ。