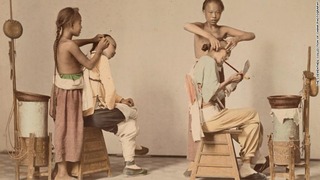太古に生きた「恐怖のクロコダイル」、恐竜食べるほどに巨大化 科学者が分析
(CNN) かつて恐竜を捕食していた巨大な爬虫(はちゅう)類の口はアリゲーターのように幅が広かったが、今は絶滅したこの生物が隆盛を誇った要因は、現代のアリゲーターが持たない特徴を備えていた点にあった。それは塩水に対する耐性だ。
デイノスクスと呼ばれるこの爬虫類は、これまで地球に生息したワニ類の中で最大の部類に属する。体長はほぼバス1台分で、生えている歯の大きさはバナナ並みだ。約8200万前から7500万年前にかけて、最強の捕食者として北米の川や入り江に暮らしていた。
学名の意味は「恐怖のクロコダイル」だが、デイノスクスは一般には「グレーター・アリゲーター」の呼称で知られる。従来の研究でも進化の系統はアリゲーターとその祖先に分類されてきた。しかし新たな化石の分析と、現在のワニ類のDNA解析を行ったところ、デイノスクスはアリゲーターやクロコダイルといった系統とは異なる区分に属することが分かった。
アリゲーターの仲間と違い、デイノスクスの体にはクロコダイル側の祖先にあった塩類腺が残っていた。そのため塩水に耐えることができたと、科学者らは23日刊行のコミュニケーションズ・バイオロジー誌で報告している。現在のクロコダイルにはこうした腺があり、体内の過剰な塩化ナトリウムを集めて放出している。
塩水への耐性のおかげで、デイノスクスはかつて北米大陸を分断していた幅1000キロ以上の西部内陸海路を泳ぐことができた。そのためデイノスクスの生息地は海路の両岸の沼地や北米の大西洋岸一帯に広がった。
デイノスクスは進化の過程で巨大化し、沼地の生態系の上位に君臨した。白亜紀の骨の化石に残った歯の痕からは、デイノスクスが恐竜を捕食していたことが示唆される。