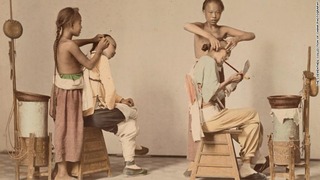「牛のおなら」ワクチンは気候変動対策にどう役立つか
(CNN) 草だけを食べて生きていける牛の能力は自然の驚異の一つだが、そこには代償も伴う。
食べた草が第一胃(牛の体内に四つある胃の一つ)で発酵する際、メタンが自然発生する。メタンは二酸化炭素の28倍の温室効果を持つ気体。二酸化炭素より短い時間で消失するが、牛のげっぷやおならを通じ平均で1頭当たり年間約90キロ放出される。糞(ふん)からも放出されるので、畜産は人間由来のメタン放出全体の3分の1を占める。メタン自体は地球温暖化の原因の約30%を占めるとされる。
一部の牧場では既に、牛の胃の中でのメタン生成低減に寄与する食品添加物を食べさせているが、それらには効き目がまちまちであることや、繰り返し与えなくてはならないなどの欠点がある。牛が自由に歩き回っていれば、添加物を常に与え続けるのは困難になる。
そこで選択肢になり得るのがワクチンだ。英国に拠点を置く家畜に特化したウイルス研究所、ピルブライト研究所は3年にわたって研究を主導し、ワクチン1種を開発している。「ワクチンが解決策の一環として魅力的なのは、非常に導入が進んでおり、一般に浸透している点だ。必要なインフラは既に整っている。人々もワクチンによって動物の健康全般に恩恵があることを理解している」。ピルブライト研究所の研究責任者を務めるジョン・ハモンド氏はそう説明する。

牛肉が関連する温室効果ガスの排出量は、主要な食料品の中で最も高い水準にある/Justin Sullivan/Getty Images/File
この国際的な取り組みは、ベゾス・アース・ファンドから940万ドルの資金援助を受けている。同ファンドは米アマゾン創業者、ジェフ・ベゾス氏の立ち上げた慈善団体で、気候変動を食い止めることを目的とする。この他、英王立獣医学校やニュージーランドの農業イノベーション研究所、アグリサーチも関わっている。
「いずれ他のワクチンと同様に広まることを期待する」とハモンド氏。「最良のシナリオは、動物への1回目のワクチン接種を比較的若いうちに行い、その効果が持続すること。目標はメタンの放出を最低でも30%減らすことだ」
一風変わったワクチン
ハモンド氏によれば、科学者たちが「牛のおならワクチン」のアイデアに取り組んでから優に10年以上の歳月が過ぎているが、ここまで目に見える結果は出ていない。「さまざまな国が相当の投資を行って、この一風変わったワクチンの開発に取り組んでいる。それは必ずしも動物にとっての利益になるとは限らないが、動物が作り出す物質の排出に関しては恩恵をもたらす」「製品は存在していないが、科学的な記述が示唆するところでは機能し得るし、実際に機能するだろう」(ハモンド氏)
「効果を得るには、ワクチンが抗体を作り出す必要がある。それがメタンを生み出す細菌と第一胃の中で結合し、それらの生成を阻止する仕組みだ」
しかしながら、その開発は極めて複雑な課題だともハモンド氏は付け加えた。抗体が第一胃の中で首尾良く働くとは認識されていないからだ。抗体とはワクチン接種後に免疫系によって作られるたんぱく質で、体外から入り込んだ物質を攻撃する。
もう一つの潜在的な問題は、動物の福祉だ。牛たちの健康に及ぼす影響を「ゼロ」とする見方は示されているものの、それはまだ実証されたわけではないと、ハモンド氏は指摘する。第一胃で吸収できる飼料の量が減少する可能性もある。その場合牛にはより多くの飼料が必要になり、畜産業者のコストを押し上げるかもしれない。
研究のゴールはこれらの問いに答えを出し、実際の薬品の開発に用いる「概念実証」を成立させることだ。ワクチンの主要な利点は、病気に対するワクチンと同様に産まれた後の子牛へ投与できることだろう。病気用のワクチンは既に使用されていると、今回のプロジェクトにも携わる英王立獣医学校の分子細胞免疫学教授、ディルク・ベルリング氏は指摘する。「ワクチンに関する適切なアプローチを突き止められれば、もしかすると母牛にワクチンを接種することも可能になるかもしれない」「実現すると、結果的に抗体の生成が初乳(子牛を産んだ後で初めて分泌される乳汁)を通じて伝達されることになるだろう。つまり数多くの方法により、牛の自己防衛機能を活用できるかもしれない。ただ現時点では、まだ何とも言えない」
誤情報の脅威
メタンの放出に対抗するワクチンは「ある種究極の目標」になると、米コーネル大学で乳牛生物学を専攻するジョセフ・マクファデン准教授は語る。1度接種すれば牛のメタン放出を長期的に低減するので、他の解決策よりも容易に実施できるというのがその理由だ。マクファデン氏は今回のプロジェクトに関与していない。
しかし、ワクチンが実行可能だとする兆候は現時点で示されていないと、同氏は付け加える。「時間をかけて多くの動物で試さなくては、この種の取り組みは機能しないだろう。一夜にして実現するものではない」
マクファデン氏によれば、ワクチンは問題を解決し得る武器の一つでしかない。他の方策としては選択的繁殖、酵素、メタンを放出する微生物の遺伝子編集、飼料添加物などが挙げられる。特に飼料添加物の取り組みは現時点で群を抜いて進んでいる。
とはいえ飼料添加物も論争と無縁ではない。紅藻を家畜に与えるとメタンが劇的に低減することを示す証拠はあるが、活性要素であるブロモホルムについての懸念も存在する。ブロモホルムは米国での分類上、「人体にとっての発がん性物質になり得る」とみられている。牛がそれを一定量食べれば牛乳にも含まれるようになるが、これまでの複数の研究で検出された水準は、人体の許容範囲を大幅に下回っていた。
マクファデン氏は紅藻について、理論上メタン放出を8~9割減らせる点を肯定的に捉える一方、飼料摂取は減少すると指摘。限定的ながら牛の健康に関する懸念もあるとの見方を示す。
昨年後半、硝酸塩をベースにした飼料添加物でブロモホルムを含まない「ボベアー」が、英国のSNSで台風の目となった。同国の乳製品大手アーラが、運営する牧場の一部でボベアーを試す意向を発表したのがきっかけだった。ボベアーの使用は承認済みで牛にとっても安全だと見なされているが、牛乳に有毒物質が残留するとの誤情報がオンライン上で拡散。牛への悪影響も取り沙汰される事態となった。これを受け英食品基準庁は、「当該の添加物は牛によって代謝されるので、牛乳に含まれることはない」とする内容の記事の公表を余儀なくされた。
ただこの反発が示すように、前出のワクチンの導入に成功しても、別の課題が発生する可能性がある。つまり誤情報や消費者の受け入れにどう対応するのかという課題だ。
「我々にはそのための準備ができていない」と、マクファデン氏。「技術の確立を目的とした科学への投資は行われているが、それらが市場に投入された後で消費者にどのように受け入れられていくのかを念頭に置いた投資は皆無だ」という。
当該のワクチンに取り組むディルク・ヴェルリング氏は、この分野で15年経験を積んできた中で、データや結果を積極的に確認しようとする人もいればそうではない人もいることが分かったと語る。その上で、主要な手法として取り入れるべきなのは、客観性のある情報の伝達だと指摘。議論にしっかりと耳を傾け、疑問に対して適切に回答することも必要になるとの認識を示した。
「新型コロナのパンデミック(世界的大流行)以降、あらゆる主題が黒か白かのみで論じられるようになったと感じる。だから我々が何を発見しようと、必ず批判する人は現れるだろう。同様に称賛する人も現れるはずだ」(ヴェルリング氏)
「最終的に、我々の取り組みが寄与し、地球温暖化に対して全体的な影響を与えられるなら、私個人の仕事としては上出来だということになる」
.jpg)