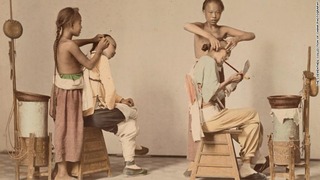フェイスブックなどSNS、視野狭め偽情報拡散の一因にも 研究論文
つまりソーシャルメディアのユーザーは、異論をはさんだり情報を提供したりするためではなく、自分が所属するグループの中で既に受け入れられている概念を再確認したり同意したりする目的で情報を共有している公算が大きい。従って、「偽ニュース」と呼ばれるデマも事実関係が確認されないまま広まってしまいかねない。
「実際に、陰謀説のような情報は、普段から代替情報源を支持していて公式発表や大手報道機関のニュースを信じないユーザーの集団の内輪のみで広まって反響する」とベッシ氏は言う。
たとえ自分は偽情報には惑わされず、開かれた姿勢を持っていると思っていても、誰もがある程度は確証バイアスの影響を受けるという。
「私たちは自分の考え方を裏付ける内容を見ると、それを気に入って共有したいと思う。私たちの認知資源や注意力、時間は限られている」(ベッシ氏)
それが内容を十分に確認しないまま軽い気持ちで共有する行動につながるといい、「例えば自分が信頼していて考え方も近い友達が投稿したというだけで、自分もその内容を投稿するかもしれない」。
将来的には誤った情報を締め出すためのプログラムやアルゴリズムが登場するかもしれないとベッシ氏は話す。しかし当面は、共有する前に自分で事実関係を確認し、自己分析を行う必要があると助言している。