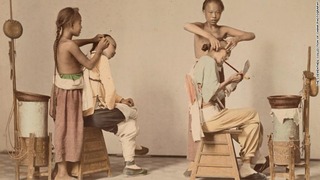太古の巨大ザメ「メガロドン」、従来の想定よりさらに長かった可能性 新研究
メガロドンは細長い体形だった可能性
島田氏らのチームは、現生のサメ145種と絶滅したサメ20種を比較し、頭部と胴体、尾部の比率のデータベースを構築。これらの比率と過去に見つかっているメガロドンの体の各部位を比べた。
「脊椎があったことは分かっている。それを胴体の全長とみなせば、現代のデータを基に頭部や尾部の長さを推定できない理由がどこにあるのか」と島田氏は問いかける。
研究チームは計算の結果、メガロドンの体形として最もあり得るモデルは、がっしりとした戦車のようなホホジロザメではなく、レモンザメなどの細長い流線形の魚だと算出。この発見をする中で、島田氏のチームは偶然にも、海洋生物学におけるより大きなパターンに遭遇していた。

新たな研究によるとメガロドンはよりレモンザメに近い流線形の体形だった可能性が高いという/Rolf von Riedmatten/imageBROKER/Shutterstock
「期せずして、我々は一部の脊椎動物が巨大化できる一方、巨大化できない脊椎動物もいる理由の謎を解明した」と島田氏は説明する。体が厚いホホジロザメは成長しても体長6メートルほど。これはずんぐりした動物が効率的に泳げる限界サイズと思われる。一方、シロナガスクジラなどのより細長い動物は、全長約30メートルの長さに成長しながらも、優れた泳ぎを実現できる。
「細身の体形を保っていれば、より大きなサイズに成長できる可能性が高まる」と島田氏は指摘。この原則はメガロドンにも当てはまり、島田氏の新たな研究によれば、メガロドンは体長は最大24メートルに達していた可能性がある一方で、従来のモデルに比べて細身だったとみられる。